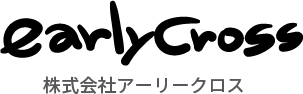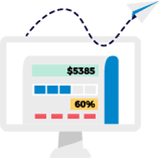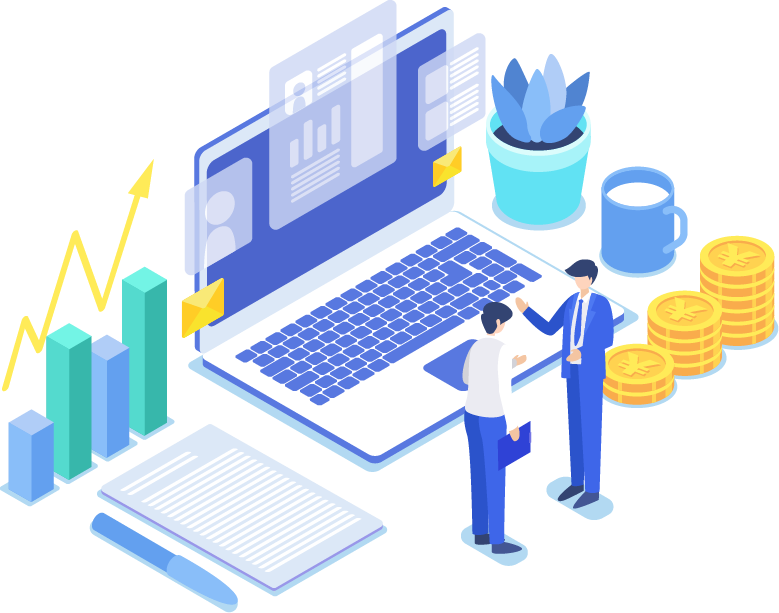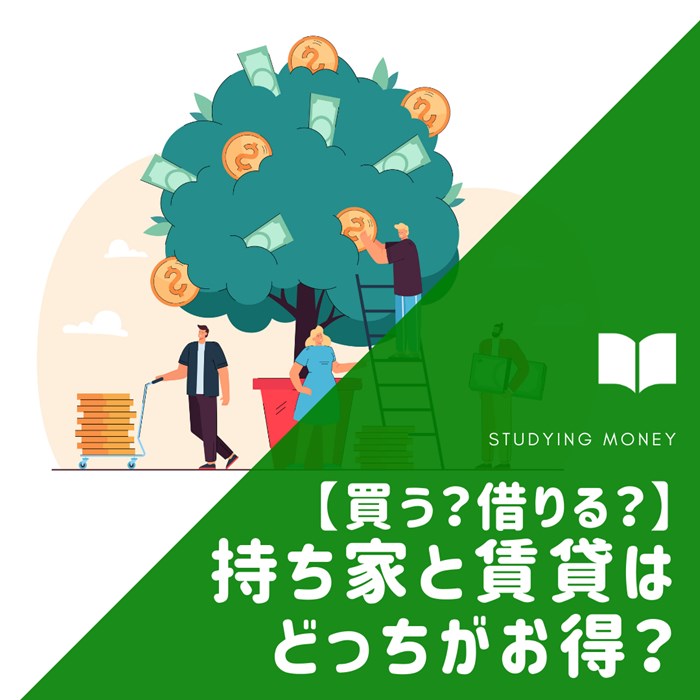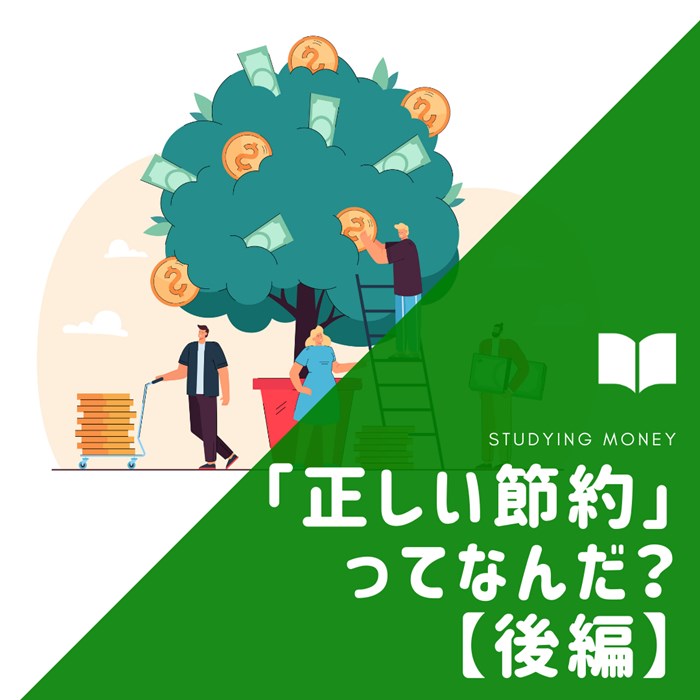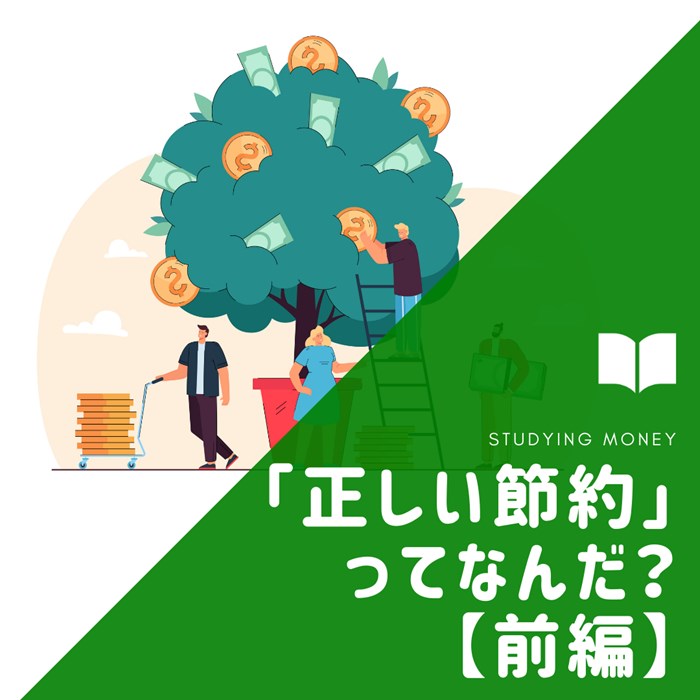2021年8月の記事一覧
Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given in /home/rcntb07/early-cross.com/public_html/wp/wp-content/themes/rcnt/content/template/cat-blog.php on line 9
- 最新の記事
-
- 福岡市主催「Z世代まるわかり会議」にて企業型DCの取組みをご紹介しました
- 企業版ふるさと納税を通じて、今帰仁村の未来づくりを応援
- 【経営者必見】数字でわかる企業型DC|5,000万円の退職金をつくる節税・資産形成の仕組み
- 株式会社アーリークロス、大阪オフィスを新設 ー 企業型確定拠出年金(DC)支援体制を拡充
- 福岡の未来をともに応援する ── 株式会社アーリークロス、アビスパ福岡のオフィシャルスポンサーに就任
- 【経営者のみなさまへ】“1日でも早く始めるべき理由”──企業型確定拠出年金(企業型DC)は「使わなければ失われる制度」です
- 企業型DCの最新動向と今後の予測について
- オフィス移転のお知らせ
- 【累計2万部突破!】中小企業経営者と従業員が抱える老後のお金の不安を解消する退職金制度解説書『得する社⻑、損する社⻑ 中⼩企業のための確定拠出年⾦』大好評発売中!
- 年末年始休業のお知らせ
- カテゴリー
-
- コンセプト(1)
- 事業内容(1)
- アーリークロスの企業型確定拠出年金(企業型DC)導入サポート(12)
- 会社案内(7)
- 企業型確定拠出年金に関するよくある質問(36)
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)について(20)
- 企業型確定拠出年金導入支援について(5)
- 個別相談について(9)
- セミナーについて(2)
- コラム(101)
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)(26)
- 資産運用(36)
- 生活に役立つ知識(20)
- 経済情報(11)
- イベントレポート(10)
- お知らせ(20)
- 企業型確定拠出年金に関する資料ダウンロード(3)
- セミナーご予約(2)
- お問い合わせ(3)
- 資料請求ありがとうございます(1)
- ご予約ありがとうございます(1)
- お問い合わせありがとうございます(1)
- サイトマップ(0)
- 未分類(0)
Contact
全国どこからでも簡単!無料!オンライン相談
企業型DCの導入・資料ダウンロードは
お問い合わせから受け付けております。
お問い合わせから受け付けております。